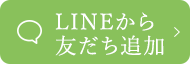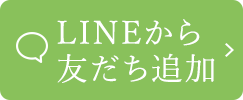味覚障害は亜鉛不足かも?|亜鉛と栄養・食事との関係とは
味覚障害は亜鉛不足かも?|亜鉛と栄養・食事との関係とは
味覚障害と亜鉛の関係|見逃されやすい栄養不足
「最近、食べ物の味が薄く感じる」「好きな料理の味が分かりにくくなった」――そんな症状を感じたことはありませんか?
もしかすると、それは「味覚障害」かもしれません。
味覚障害の原因はさまざまですが、近年注目されているのが亜鉛不足です。この記事では、亜鉛と味覚障害の関係、亜鉛を多く含む食品、そして日常での注意点などを詳しく解説します。
亜鉛とは?|体に必要な“微量必須ミネラル”
亜鉛は、体内で酵素の働きを助けたり、細胞分裂や新陳代謝、免疫機能を支えるなど、生命活動に欠かせないミネラルのひとつです。
特に味を感じる“味蕾(みらい)”の再生に深く関わっており、亜鉛が不足すると味覚の異常が生じやすくなるといわれています。
味覚障害の患者さんの中には、血中の亜鉛濃度が低下しているケースも多く報告されています。
銅との関係も重要です|亜鉛のサプリメント使用時は注意
亜鉛とセットで気をつけたいのが「銅」とのバランスです。
過剰な亜鉛摂取は、銅の吸収を妨げ、逆に「銅欠乏症」を招くこともあります。サプリメントなどで亜鉛を摂る場合は、医師や薬剤師に相談のうえで適切に使用することが大切です。
亜鉛はどんな食品に多く含まれている?
亜鉛は以下のような食品に多く含まれています。
-
牡蠣(かき):代表的な高亜鉛食品
-
牛肉・豚レバー
-
納豆・豆類
-
チーズ
-
ナッツ類(アーモンド、カシューナッツなど)
ただし、インスタント食品や加工食品に偏った食事では亜鉛摂取が不足しやすくなります。バランスの取れた食生活が基本です。
亜鉛欠乏で起こる症状は?
亜鉛が不足すると、次のような症状があらわれることがあります:
-
味覚障害(味がわかりにくくなる、何を食べてもおいしくない)
-
食欲不振
-
皮膚炎や脱毛
-
傷の治りが遅い
-
免疫力の低下(風邪をひきやすい)
特に高齢者、偏食傾向のある方、胃を切除した既往のある方、慢性腎疾患の方は、亜鉛不足のリスクが高いとされています。
味覚の変化に気づいたら、日進市のたがやクリニックへ早めにご相談を
味覚の異常は、生活の質(QOL)を大きく低下させる症状です。しかし原因がわかれば、栄養指導や適切な治療で改善できる場合も多くあります。
たがやクリニックでは、栄養の専門知識を持つ医師や管理栄養士が、血液検査や生活習慣のチェックを通じて、根本的な改善を目指します。
日進市、長久手市、東郷町、みよし市など、地域の皆さまの健康を守るパートナーとして、いつでもお気軽にご相談ください。