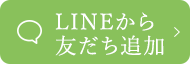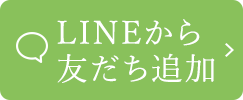お茶の違い、どのお茶が健康的?お茶と高カリウム血症のリスク(日進市・長久手市・みよし市・東郷町)
お茶の違い、どのお茶が健康的?お茶と高カリウム血症のリスク(日進市・長久手市・みよし市・東郷町)
お茶の違いは「発酵度」「原料」「カフェイン量」
お茶と一口に言っても、緑茶・紅茶・ウーロン茶・麦茶・ルイボスティーなどさまざま。
実は「茶葉から作る茶」と「穀物や豆から作るお茶(ティー飲料)」に大きく分かれます。
-
・茶葉系のお茶(チャノキ):緑茶、ウーロン茶、紅茶、ほうじ茶、ジャスミン茶など
-
・ノンカフェインの飲み物:麦茶、ルイボスティー、黒豆茶、ハーブティーなど
この違いにより、健康効果・カフェイン量・風味が変わります。
茶葉から作るお茶(カフェインあり)
緑茶(不発酵茶)
カテキンが豊富で健康効果が高い代表格
日本人に最も馴染み深い緑茶は、カテキン(EGCG)が豊富。
期待される健康効果:
-
・抗酸化作用で生活習慣病予防
-
・血糖値・コレステロールの改善
-
・免疫サポート(抗ウイルス作用)
-
・集中力向上(適度なカフェイン)
ただし、胃が弱い方・妊娠中の方はカフェイン量に注意が必要です。
ほうじ茶(焙煎茶)
カフェイン少なめで胃にやさしく飲みやすい
緑茶を強く焙煎したお茶で、香ばしい風味が特徴。
カフェインが他の茶より少なく、夜でも飲みやすいです。
期待される効果:
-
・胃への刺激が少ない
-
・香り成分によるリラックス効果
ウーロン茶(半発酵茶)
脂っこい食事が多い方におすすめ
ウーロン茶特有のポリフェノールが、脂肪吸収抑制に働くことが知られています。
期待される効果:
-
・食事性脂肪の吸収抑制
-
・脂肪燃焼の促進
-
・さっぱりした口当たりで食事と相性良好
紅茶(発酵茶)
発酵由来のポリフェノールが豊富
紅茶に含まれるテアフラビンは、腸内環境改善や抗酸化作用が特徴。
期待される効果:
-
・リラックス効果(香り)
-
・腸内細菌バランス改善
-
・血糖・血圧へよい影響
ジャスミン茶(緑茶+花の香り)
香りによるストレス軽減
緑茶をベースにジャスミンの香りを付けたお茶。
香り成分にはリラックス作用があります。
期待される効果:
-
・自律神経を整える
-
・ストレス軽減
-
・緑茶由来のカテキン効果も期待
ノンカフェインのお茶(子ども・妊娠中にも安心)
麦茶(焙煎大麦)
夏の定番・ノンカフェインでミネラル補給にも
麦茶は大麦を焙煎した飲料で、カフェインゼロ。
ミネラルが含まれ、体を冷やす作用があると言われ、夏場に最適です。
期待される効果:
-
・ノンカフェインで飲みやすい
-
・胃にやさしい
-
・熱中症予防の水分補給に適している
※血圧を下げるカリウムはそこまで多くはありません。
ルイボスティー(南アフリカ原産のハーブ)
抗酸化作用が強く、アレルギー症状にも良いとの報告
「発酵ルイボス」「グリーンルイボス」に分かれ、ポリフェノールが豊富。
期待される効果:
-
・抗酸化作用
-
・アレルギー症状の緩和が期待
-
・カフェインゼロで妊娠中も可
黒豆茶
ポリフェノール・イソフラボンが豊富
黒豆を焙煎した香ばしいお茶で、こちらもカフェインゼロ。
期待される効果:
-
・抗酸化作用
-
・血圧・コレステロール改善の報告
-
・香り・味わいに癒し効果
結局どのお茶が健康にいいの?
目的別のおすすめは以下の通り。
-
・生活習慣病予防 → 緑茶
-
・食事の脂肪が気になる → ウーロン茶
-
・リラックスしたい → 紅茶・ジャスミン茶
-
・子ども・妊娠中 → 麦茶・ルイボス・黒豆茶
-
・カフェイン控えめが良い → ほうじ茶
どれも健康効果がありますが、
「体質・生活スタイルに合ったものを続ける」が最も大切です。
お茶と高カリウム血症のリスクについて(腎臓病の方は要注意)
一般的に、お茶は水分補給として安全に飲むことができますが、慢性腎臓病(CKD)や高カリウム血症のリスクがある方は注意が必要です。
緑茶・ほうじ茶・麦茶など、多くのお茶はコーヒーに比べるとカリウム量は少なめですが、1Lあたり20〜70mgほどのカリウムを含むものもあります。通常の腎機能の方であれば問題ありませんが、腎臓の働きが落ちてくると、「少量のカリウムが積み重なって血中カリウムが上昇する」ことがあります。
特に以下の方は注意してください:
-
・CKDステージ3以降
-
・高カリウム血症を指摘されたことがある方
-
・ACE阻害薬、ARB、スピロノラクトン等を服用中の方
また、濃いお茶を大量に飲む(1日2〜3L)と、カリウムだけでなくシュウ酸負荷も増え、腎結石や腎機能悪化のリスクが上がることもあります。
安全のためのポイント:
-
・1日の摂取量はコップ2~3杯程度に調整
-
・「濃いお茶」より麦茶・玄米茶・ほうじ茶の方が比較的カリウムは少なめ
-
・心配な方は診察時に普段飲んでいるお茶の種類と量をお知らせください
腎臓病の方でも適切に選べばお茶を楽しむことは可能です。ご不安があれば、たがやクリニックでお気軽にご相談ください。