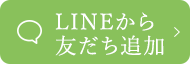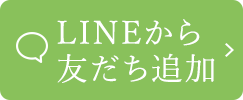カリウムと血圧の関係 ~塩分だけでなく「カリウムバランス」も大切~
カリウムと血圧の関係 ~塩分だけでなく「カリウムバランス」も大切~(日進市・長久手市・みよし市・東郷町)
血圧とカリウムの深い関係
「塩分(ナトリウム)を控えると血圧が下がる」という話はよく知られていますが、実は「カリウムを十分に摂る」ことも血圧管理にとってとても重要です。
カリウムは、体内のナトリウムを尿中に排泄し、血管の緊張を和らげることで血圧を下げる効果があります。
つまり、塩分を減らすだけでなく、カリウムを増やすことが高血圧予防の大切なポイントなのです。
カリウムとは?どんな働きをしているのか
カリウムは、私たちの体の中で「細胞の中のミネラル」として働いています。
主な役割は以下の通りです。
-
・ナトリウムとのバランスを保ち、血圧を調整する
-
・神経や筋肉の正常な働きをサポートする
-
・余分な塩分を尿として排出する
カリウムが不足すると、ナトリウムが体内にたまりやすくなり、血圧が上がりやすくなります。
カリウムを多く含む食品
カリウムは、野菜・果物・豆類などに多く含まれます。
代表的な食品は以下の通りです。
| 食品 | カリウム含有量(100gあたり) | 備考 |
|---|---|---|
| バナナ | 約360mg | 手軽に摂取可能 |
| ほうれん草 | 約690mg | ゆでても豊富 |
| トマト | 約210mg | サラダにもおすすめ |
| じゃがいも | 約410mg | 加熱しても比較的残る |
| 大豆製品(納豆・豆腐) | 約500~700mg | 良質なたんぱく源 |
| みかん・キウイ | 約250~300mg | 果物からも補給可 |
食事の中で、「減塩+野菜や果物をしっかり摂る」ことが、最も自然な形での血圧コントロールにつながります。
摂りすぎに注意が必要な人も
腎臓の働きが低下している方(慢性腎臓病・CKDなど)は、カリウムをうまく排出できず「高カリウム血症」を起こすことがあります。
血中カリウムが高くなりすぎると、心臓の不整脈を起こすおそれがあるため注意が必要です。
そのため、腎臓病や糖尿病性腎症などをお持ちの方は、自己判断でカリウムを多く摂るのは避けましょう。
たがやクリニックでは、血液検査でカリウム値や腎機能を確認しながら、食事内容を一緒に検討します。
カリウムが血圧を下げる理由
カリウムには、次のような血圧を下げるメカニズムがあります。
-
1.体内の余分なナトリウムを排出する
-
2.血管を拡げる作用
-
3.細胞内外の電解質バランスを整え、心臓や腎臓の負担を減らす
これらの作用が重なり、カリウム摂取量が多い人では、血圧が安定しやすくなることが多くの研究で示されています。
カリウムのナトリウム再吸収抑制効果と尿細管での作用機序
カリウムによる血圧低下の根幹には、腎臓におけるナトリウム再吸収抑制(ナトリウレシス)が関与します。
この現象は尿細管各部位で複雑に制御されており、以下のような機序が知られています。
-
・近位尿細管(Proximal Tubule)
高カリウム環境では、Na⁺/H⁺交換体(NHE3)の発現と活性が抑制され、Na⁺再吸収が減少します。 -
・遠位尿細管~集合管(DCT、CNT、CCD)
カリウム上昇により、WNK1/4–SPAK/OSR1経路が抑制され、NaCl共輸送体(NCC)の活性が低下します。
結果としてNa⁺再吸収が減少し、尿中Na⁺排泄が促進されます。これはチアジド系利尿薬と同様の作用と考えられます。 -
・集合管での電位変化
高K⁺状態ではROMKおよびBKチャネルを介したK⁺分泌が亢進し、管腔内の電位変化によりNa⁺再吸収がさらに抑制されます。
これらの尿細管レベルの調節により、カリウム摂取はナトリウム排泄を促し、細胞外液量を減少させ、結果的に血圧を低下させます。
日進市のたがやクリニックへご相談ください
たがやクリニックでは、血圧管理や腎臓の健康を重視した生活指導を行っています。
「血圧がなかなか下がらない」「腎臓の数値が気になる」「塩分を控えても効果が出ない」――そんな方は、カリウムの摂取バランスが関係しているかもしれません。
血圧・腎臓の専門医が、食事・運動・お薬を含めてトータルでサポートいたします。お気軽にご相談ください。