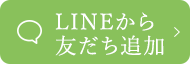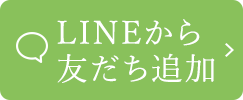便秘とカリウムの意外な関係 〜腎臓と腸の連携を意識した管理〜【日進市・長久手市・みよし市・東郷町】
便秘とカリウムの意外な関係 〜腎臓と腸の連携を意識した管理〜【日進市・長久手市・みよし市・東郷町】
カリウム値は便と関係?
慢性腎臓病(CKD)や高カリウム血症の患者さんでは、「食事」や「薬」だけでなく、便通の状態もカリウムのコントロールに関わっています。
腎臓からの排泄が低下してくると、腸からのカリウム排泄が代わりに増えていくことが知られています。
本記事では、腎臓専門医の立場から、便秘とカリウムの関係について最新の知見を交えて解説します。
カリウムの排泄経路 ― 腎臓だけではない
カリウムは主に腎臓から尿中に排泄されますが、腎機能が低下すると、大腸から便として排泄される割合が増えます。
腎機能低下と便中排泄の関係
特にCKDステージ4以降では、便中排泄が全体の20〜30%に達するという報告もあります。
つまり、便秘が続くと体内にカリウムが滞留しやすくなる可能性があるのです。
腎臓と腸が互いに補い合うこの仕組みは、「腎腸連関」として近年注目されています。
カリウム吸着薬 ― 適切に使えば強力な味方
カリウム吸着薬の働き
高カリウム血症の治療では、カリウム吸着薬がよく用いられます。
これらは腸管内でカリウムを吸着し、便とともに排泄させる薬剤で、血中カリウム濃度を下げる効果があります。
新しい薬の安全性と注意点
新しいタイプの吸着薬(パチロマーやジルコニウムシクロシリケート)は、副作用が少なく安全性が高いことが報告されています。
一方で、従来の薬剤では便秘や膨満感などの副作用がみられることもあります。
重要なのは、「薬をやめる」ことではなく、下剤や水分摂取を併用しながら便通を整えて使うことです。
カリウム吸着薬は、正しく使えば腎臓を守る心強い味方です。
腸と腎臓の関係 ― “腎腸連関”という考え方
近年、「腎腸連関(gut-kidney axis)」という概念が注目されています。
腎腸連関とは
腎機能が低下すると、腸内環境が乱れ、尿毒素産生菌が増加し、腸粘膜のバリア機能が低下します。
逆に、腸内環境を整えることで腎臓の代謝負担を減らし、炎症や尿毒素の蓄積を抑える効果が期待されています。
つまり、腸の健康を守ることが腎臓の健康を守ることにつながるのです。
食物繊維の摂取 ― 便秘改善とカリウムのジレンマ
食物繊維とカリウムの関係
便通を良くするために食物繊維を摂ることは効果的ですが、野菜や果物にはカリウムが多く含まれています。
そのため、腎臓病の方では「食物繊維を摂りたいけれどカリウムが心配」という悩みが生じやすいです。
上手な工夫
-
・ゆでこぼしや水さらしでカリウムを減らす
-
・低カリウム野菜(キャベツ・きゅうり・もやしなど)を選ぶ
-
・おからやきのこ類など、比較的カリウムが少ない食物繊維源を活用する
無理なくバランスを取りながら、腸内環境を整えていくことが大切です。
排便コントロールの工夫
日常生活でできる便通改善
便秘を防ぐには、薬だけでなく生活習慣の工夫も重要です。
-
・朝食後にトイレに行く「排便リズム」をつくる
-
・十分な水分をとる
-
・トイレでいきまず、自然な排便を心がける
日進市のたがやクリニックへご相談ください
-
・CKDでは便からのカリウム排泄が重要になる
-
・カリウム吸着薬は便秘対策と併用すれば安全に使える
-
・便秘は高カリウム血症のリスクになる
-
・食物繊維摂取はカリウム量に注意しながら調整を
-
・腸と腎臓は密接に関係しており、「腎腸連関」を意識した管理が大切
腎臓の治療というと「血液・尿検査中心」と思われがちですが、実は日々の便通の管理も腎臓を守る大切なポイントです。
カリウム値や便秘のことでお悩みの方は、日進市のたがやクリニックへご相談ください。