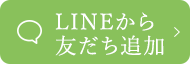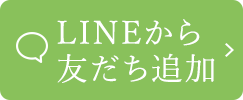口腔内フレイルと慢性腎臓病・糖尿病の深い関係|全身の健康を守るために知っておきたいこと
口腔内フレイルと慢性腎臓病・糖尿病の深い関係|全身の健康を守るために知っておきたいこと
最近注目されている「口腔内フレイル」という言葉をご存じでしょうか。
加齢や生活習慣などで口腔機能が徐々に低下し、噛む力・飲み込む力・発声などが衰える状態を指します。
最新の研究では、この口腔内フレイルが慢性腎臓病(CKD)や糖尿病の発症・進行と深く関わっていることがわかってきました。
口腔内フレイルとは?
口腔内フレイルは「心身のフレイル(虚弱)」の初期段階として位置づけられています。
主な特徴は以下の通りです。
-
噛む力の低下(咀嚼機能の低下)
-
飲み込みにくさ(嚥下障害の初期)
-
滑舌や発声の衰え
-
口の中の乾燥(ドライマウス)
-
食欲や食事量の減少
これらは一見「年齢のせい」と思われがちですが、放置すると栄養不足や筋力低下を招き、全身の健康に悪影響を与えます。
口腔内フレイルと慢性腎臓病(CKD)の関係
慢性腎臓病は腎機能が徐々に低下していく病気で、日本では成人の約5人に1人が該当するといわれています。
近年のガイドラインや研究では、以下の関連が報告されています。
-
歯周病菌が全身に炎症を起こす
歯周病は口腔内フレイルの一因であり、慢性炎症を介して腎機能低下を促進すると考えられています。 -
低栄養が腎機能悪化のリスクに
噛みにくさや嚥下障害によってたんぱく質摂取が不足し、筋肉量や代謝が落ちます。 -
透析患者での口腔機能低下率が高い
CKDの進行に伴い、口腔乾燥や味覚異常が生じやすく、さらにフレイルが加速します。
口腔内フレイルと糖尿病の関係
糖尿病は高血糖状態が続き、血管や神経にダメージを与える病気です。
口腔内フレイルとの関係には以下のポイントがあります。
-
高血糖は歯周病の進行を促進
歯周病は糖尿病の「第6の合併症」と呼ばれ、相互に悪影響を与えます。 -
咀嚼機能低下で食事バランスが乱れる
柔らかい炭水化物中心の食事に偏り、血糖コントロールが悪化します。 -
炎症性サイトカインの増加
歯周病による炎症物質が血中に放出され、インスリン抵抗性を悪化させます。
最新情報
-
厚生労働省の調査では、口腔機能の低下はCKDや糖尿病の有病率と有意に関連することが示されています。
-
日本歯科医師会の報告によると、歯周病治療により糖尿病患者のHbA1cが平均0.4%改善するとの結果があります。
-
2023年の国際腎臓学会(ISN)発表では、口腔ケア介入がCKD患者の炎症マーカー(CRP)を低下させる可能性が報告されました。
予防と対策
-
定期的な歯科受診と口腔ケア
歯石除去や歯周病治療は口腔内フレイル予防の基本です。 -
バランスの取れた食事
噛みごたえのある食品も取り入れ、咀嚼機能を維持します。 -
口腔体操や発声練習
唇や舌を動かす体操は筋肉の衰え防止に有効です。 -
内科と歯科の連携
CKD・糖尿病の管理には、口腔機能の維持が重要です。
日進市のたがやクリニックへご相談ください
口腔内フレイルは、単に「口の中だけの問題」ではなく、慢性腎臓病や糖尿病と密接に関わる全身の健康課題です。
早期からの予防と対策で、健康寿命の延伸が期待できます。
たがやクリニックでは、腎臓病・糖尿病の診療とともに、地域の歯科医療機関と連携しながら、口腔内フレイルの予防に取り組んでいます。