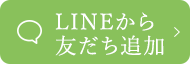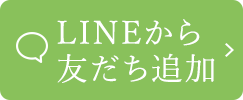吐き気止めはどうやって効くの?注意点は?
吐き気止めはどうやって効くの?注意点は?
~日進市・長久手市・みよし市・東郷町で内科をお探しの方へ~
吐き気はなぜ起こるのか
「吐き気(悪心)」や「嘔吐」は、胃腸の不調だけでなく、脳や内耳(めまい)、薬の副作用、ストレスなど、さまざまな要因で起こります。
体の中では「延髄(えんずい)」という脳の部分にある嘔吐中枢が関係しています。ここに「吐き気の信号」が集まり、一定の刺激を超えると吐き気や嘔吐が起こります。
吐き気止め(制吐薬)の基本的な働き
吐き気止めは、この「嘔吐中枢」やその周辺の神経伝達をブロックして、吐き気の信号を抑える薬です。
原因に応じて、作用する部位や使われる薬の種類が異なります。
主な吐き気止めの種類と作用の仕組み
ドパミン受容体遮断薬(メトクロプラミドなど)
延髄にある化学受容体引金帯(CTZ)で、ドパミン受容体(D2受容体)を遮断します。
胃の動きを整える作用もあり、胃もたれや食後のムカつきにも使われます。
セロトニン受容体拮抗薬(オンダンセトロンなど)
抗がん剤や手術後の強い吐き気に対して使われるタイプ。
セロトニン(5-HT3)受容体をブロックし、消化管やCTZへの刺激を抑えます。
抗ヒスタミン薬・抗コリン薬(ジフェンヒドラミン、スコポラミンなど)
内耳の平衡感覚の異常による吐き気、いわゆる「乗り物酔い」や「めまい」に有効です。
脳内でヒスタミン(H1)やアセチルコリンの作用を抑えます。
ニューロキニン受容体拮抗薬(アプレピタントなど)
比較的新しいタイプで、サブスタンスP(SP)という神経伝達物質の作用を抑えることで、強い吐き気を防ぎます。
抗がん剤による遅発性嘔吐などに使われます。
吐き気止めの注意点
薬の使い分けが大切
吐き気の原因はさまざまなので、「どの部位のどの神経が関与しているか」を考えて薬を選ぶことが重要です。
胃腸の不調・めまい・薬剤性など、原因によって効く薬が異なります。
副作用に注意
ドパミン遮断薬では眠気・ふらつき・錐体外路症状(手足のこわばりなど)が起こることがあります。
抗ヒスタミン薬や抗コリン薬では口の渇き・便秘・排尿困難などにも注意が必要です。
特に高齢の方は慎重に使う必要があります。
自己判断での長期使用は避けましょう
吐き気止めで一時的に症状が和らいでも、根本の原因(胃潰瘍、感染、脳の病気など)が隠れていることがあります。
症状が続く場合は早めに医療機関で原因を確認しましょう。
吐き気止めを安全に使うために
-
・医師の指示に従い、原因に合った薬を使う
-
・長期の使用や複数の薬の併用は避ける
-
・妊娠中・授乳中の方は必ず医師に相談する
日進市のたがやクリニックでは、症状の背景を丁寧に診断し、最適な薬の選択や生活指導を行っています。お困りの方はお気軽にご相談ください。