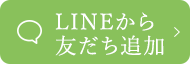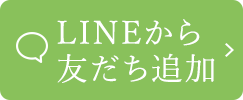塩分量の“正しい見方”できていますか?NaとNaClの違いを解説
塩分量の“正しい見方”できていますか?NaとNaClの違いを解説
塩分表示の「Na」と「食塩相当量」…実は違うものです
食品ラベルを読む際、「ナトリウム(Na)」と「食塩相当量(g)」を同じ意味だと思っていませんか?
実はこの2つは全く違う情報であり、減塩を正しく実践するためにはその違いを理解することがとても重要です。
生活習慣病の増加とともに、塩分摂取量の見直しは大きなテーマになっています。
Na(ナトリウム)とNaCl(食塩)の違い
Naは“成分のひとつ”、NaClは“塩そのもの”
-
・Na(ナトリウム):塩の構成要素のひとつ
-
・NaCl(塩化ナトリウム):私たちが“塩”と呼ぶ物質そのもの
そのため、ナトリウム量だけでは実際の塩分量は分かりません。
ナトリウム量を食塩相当量に換算する方法
食品表示がNa表記の場合は必ず換算が必要
食塩相当量(g)= ナトリウム量(mg) × 2.54 ÷ 1000
換算例(ナトリウム 800mg の食品の場合)
0.8 × 2.54 = 約2.0gの食塩
この違いを知らずに
「ナトリウム量が少ないから大丈夫」
と誤解している方も多く、実は2〜3倍の塩分を摂っていたケースも珍しくありません。
「食塩相当量」と表記されている場合はそのまま信頼してOK
ただし“100gあたり”や“複数食分”に注意
最近は「食塩相当量」での表記が一般的になってきました。
この場合は換算不要ですが、
-
・1袋=2食分
-
・100gあたりの表示
-
・惣菜で実際の量が分かりにくい
などの“落とし穴”があるため、量の確認は必須です。
減塩食品でもNaに注意が必要です
ナトリウム化合物が含まれる場合がある
減塩と書かれていても、
-
・グルタミン酸ナトリウム
-
・リン酸ナトリウム
-
・炭酸ナトリウム
など調味料・添加物としてのナトリウムが使われている場合があります。
確認すべきポイント
最終的には
「食塩相当量(g)」の数値を見るのが最も正確
です。
日本高血圧学会の減塩目標は“1日6g未満”
日本人の平均摂取量は約10g/日
日本高血圧学会(JSH)は“6g未満/日”を推奨していますが、実際には多くの方が目標の2倍近く摂取しています。
塩分が多い食品の例
-
・外食(特に麺類)
-
・コンビニ弁当
-
・パン、ハム、ソーセージ
-
・インスタント食品
-
・漬物、味噌汁
毎日の「少しずつ」が積み重なり、食塩過剰の原因になっています。
食塩量を減らすコツ
今日からできる簡単な工夫
-
・スープは残す
-
・麺類は週1〜2回まで
-
・調味料は“かける”より“つける”
-
・減塩しょうゆを活用
-
・だしを活かして味付けを薄く
-
・加工食品を控え、素材から調理
無理なく続く減塩を心がけましょう。
日進市・長久手市・みよし市・東郷町で減塩指導をご希望の方へ
専門医が数値の見方から食事の工夫までサポートします
たがやクリニックでは
-
・高血圧
-
・CKD(慢性腎臓病)
-
・糖尿病
-
・メタボリック症候群
の患者さんを対象に、塩分摂取量の評価・生活指導を行っています。
食品表示の見方がよくわからない方も、お気軽にご相談ください。