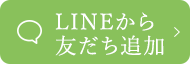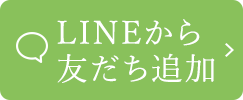慢性腎臓病と代謝性アシドーシス|酸塩基バランスの乱れに注意を
慢性腎臓病と代謝性アシドーシス|酸塩基バランスの乱れに注意を【日進市・長久手市・みよし市・東郷町】
慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の機能が少しずつ低下していく病気です。
実は、腎臓の機能が下がると「酸塩基(さんえんき)バランス」が崩れやすくなることをご存じでしょうか?
この「酸と塩基のバランス」は、体内の化学反応や代謝を正常に保つうえでとても大切です。
この記事では、腎臓と代謝性アシドーシスの関係を解説します。
酸塩基バランスとは?
私たちの体は、血液の「pH(ペーハー)」をほぼ一定に保っています。
このバランスを「酸塩基平衡」といいます。
-
・pHが下がる(酸性に傾く)=アシドーシス
-
・pHが上がる(アルカリ性に傾く)=アルカローシス
腎臓と肺が協力して、このバランスを調整しています。
肺は「二酸化炭素」を排出して酸の量をコントロールし、腎臓は「酸を排泄」し「重炭酸(HCO₃⁻)」を再吸収して、体内のpHを保っています。
慢性腎臓病と代謝性アシドーシスの関係
慢性腎臓病が進むと、腎臓が酸をうまく排泄できなくなります。
すると血液が「酸性」に傾き、「代謝性アシドーシス」という状態になります。
代謝性アシドーシスになると…
-
・筋肉の分解が進みやすい →サルコペニアを助長
-
・骨がもろくなる → 骨密度低下
-
・腎機能の低下がさらに進む → 腎機能低下の加速
-
・インスリンの効きが悪くなる → 糖代謝悪化
といった悪影響が報告されています。
治療と予防
軽度の代謝性アシドーシスでは、生活習慣の改善と定期的な血液検査で経過をみます。
pHや重炭酸の値(HCO₃⁻)が下がっている場合、重炭酸ナトリウム(炭酸水素ナトリウム)などの薬を使って補正します。
また、野菜や果物に多く含まれる「アルカリ性の食品」を意識して摂ることも効果的です。
(ただし、カリウム制限がある方は主治医にご相談ください。)
食生活と生活の工夫
-
・野菜・果物をバランスよく(制限がなければ)
-
・加工食品・肉類・塩分を控えめに
-
・定期的に血液検査を受け、重炭酸値を確認
-
・適切な水分を摂取(医師の指示に従って)
腎臓の機能が低下している方では、こうした日常の工夫が将来の腎機能の保護につながります。
日進市のたがやクリニックへご相談ください
慢性腎臓病の方では、「代謝性アシドーシス」は見逃されがちですが、放置すると腎臓や全身に悪影響を及ぼします。
定期的な採血で血液の酸塩基バランスをチェックし、必要に応じて早めの対応を行うことが大切です。
たがやクリニックでは、腎臓専門医が慢性腎臓病(CKD)の進行予防から生活指導、治療まで一貫してサポートしています。どうぞお気軽にご相談ください。
糖尿病性腎症の“四本柱(Four Pillars)”とは? 心腎保護をめざす最新治療戦略
便秘とカリウムの意外な関係 〜腎臓と腸の連携を意識した管理〜