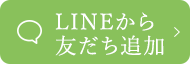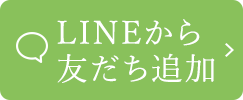抗アレルギー薬の注意点とは?緑内障や前立腺肥大がある時|日進市のたがやクリニックが解説
抗アレルギー薬の注意点とは?緑内障や前立腺肥大がある時|日進市のたがやクリニックが解説
抗アレルギー薬とは
抗アレルギー薬は、花粉症・アレルギー性鼻炎・じんましん・気管支喘息などに用いられる薬で、アレルギー反応を抑えて症状を和らげる役割があります。
抗ヒスタミン薬の「世代」の違い
抗アレルギー薬の中心となるのが「抗ヒスタミン薬」です。大きく2つの世代に分けられます。
-
第1世代抗ヒスタミン薬
眠気・口の渇き・便秘などの副作用が強く出やすい薬です。かゆみ止めや鼻水の抑制には効果的ですが、現在は長期使用にはあまり推奨されません。 -
第2世代抗ヒスタミン薬
副作用を軽減し、日常生活に支障が出にくいよう改良された薬です。眠気が少なく、花粉症やじんましんの治療でよく処方されています。
抗アレルギー薬を使用する際の注意点
1. 眠気・集中力の低下
第1世代に特に強く、第2世代でも個人差があります。運転や危険を伴う作業には注意が必要です。
2. 他の薬との飲み合わせ
抗うつ薬・抗不安薬・睡眠薬・アルコールなどと併用すると、副作用が強まる可能性があります。
3. 緑内障の方への注意
一部の抗ヒスタミン薬は眼圧を上げる可能性があり、特に「閉塞隅角緑内障」の方には使用を避ける必要があります。緑内障の種類や治療状況によって対応が異なるため、必ず眼科と連携して使用の可否を判断します。
比較的安全とされる第2世代抗ヒスタミン薬の例
-
フェキソフェナジン(アレグラ®)
-
ロラタジン(クラリチン®)
-
デスロラタジン(デザレックス®)
-
ビラスチン(ビラノア®)
→ これらは抗コリン作用がほとんどなく、眠気も少ないため、緑内障の方にも処方されやすいです。
※安全に使える薬がありますが、病状や眼科の治療状況によって変わるので必ず相談してください。
4. 前立腺肥大症の方への注意
抗ヒスタミン薬には抗コリン作用があるため、前立腺肥大による排尿障害を悪化させることがあります。尿が出にくい・残尿感がある方は、医師に必ず相談してください。
比較的安全とされる薬(抗コリン作用が少ない)
-
フェキソフェナジン(アレグラ®)
-
ロラタジン(クラリチン®)
-
デスロラタジン(デザレックス®)
-
ビラスチン(ビラノア®)
→ 緑内障と同じく、抗コリン作用が弱い第2世代抗ヒスタミン薬が適しています。
※安全に使える薬がありますが、病状や泌尿器科の治療状況によって変わるので必ず相談してください。
5. 妊娠・授乳中の使用
妊娠中や授乳中でも使用できる薬はありますが、限られています。自己判断せずに医師へご相談ください。
6. 小児や高齢者への注意
小児は体重・年齢に応じた調整が必要で、高齢者では眠気やふらつきによる転倒リスクが高まります。
日常生活での工夫
-
花粉シーズンは外出時にマスク・眼鏡を使用
-
帰宅時はうがい・洗顔で花粉を落とす
-
眠気がある薬を服用した日は運転を避ける
よくある質問(Q&A)
Q1. 第1世代と第2世代はどちらが良いですか?
A. 日常生活への影響を考えると第2世代が中心になります。ただし症状の種類や強さによって第1世代が有効な場合もあります。
Q2. 緑内障や前立腺肥大でも薬は飲めますか?
A. 種類や重症度によって使える薬と使えない薬があります。必ず現在の病気や服薬状況をお伝えください。
Q3. 花粉症の薬はいつから飲むべき?
A. 症状が出てからでは遅く、花粉が飛び始める少し前から飲み始める「初期療法」が効果的です。
日進市・長久手市・みよし市・東郷町のアレルギー症状でお悩みの方へ
たがやクリニックでは、じんましんや花粉症などに対し、患者さんの体質・基礎疾患・ライフスタイルに合わせた抗アレルギー薬を処方しています。
緑内障や前立腺肥大など他の病気をお持ちの方も、安心してご相談ください。