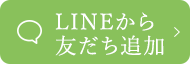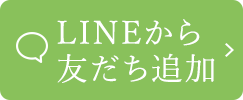梅干しの注意点と最新の健康トレンド|日進市・長久手市・みよし市・東郷町で健康を意識する方へ
梅干しの注意点と最新の健康トレンド|日進市・長久手市・みよし市・東郷町で健康を意識する方へ
梅干しは体に良いけれど「注意点」もあります
梅干しは古くから日本人の食卓に欠かせない存在で、抗菌作用や疲労回復、整腸作用など多くの健康効果が期待されます。しかし、体に良いイメージが強い一方で、いくつか注意点もあります。特に高血圧や腎臓病のある方は摂取量に気をつける必要があります。
梅干しに含まれる塩分はどのくらい?
昔ながらの梅干しは塩分濃度が15〜20%程度と非常に高く、1粒で1〜2gの塩分を含むこともあります。近年は減塩志向の高まりから、塩分5〜8%程度の「減塩梅干し」が主流になりつつあります。ただし、減塩の分、保存料や調味料が加えられていることもあるため、成分表示を確認することが大切です。
カリカリ梅との違いは?
柔らかい伝統的な梅干しと、歯ごたえのある「カリカリ梅」では製法が異なります。カリカリ梅はクエン酸カルシウムを加えて漬け込むことで、パリッとした食感になります。間食やおやつとして人気ですが、添加物や塩分量が高い製品もあるため、食べ過ぎには注意が必要です。
自分でつくると安心?
最近は「発酵食品を自宅で仕込む」ブームもあり、梅干しを自分で漬ける方も増えています。手作りの場合、塩分や添加物をコントロールできる点がメリットです。また、赤じそを加えることでポリフェノールの一種であるアントシアニンを摂取でき、抗酸化作用も期待できます。
健康へのメリット
梅干しに含まれる「クエン酸」は疲労回復に効果的で、スポーツや暑い時期の熱中症予防にも注目されています。さらに近年の研究では、梅のポリフェノールが血糖値の上昇を緩やかにする可能性も報告されています。ただし、健康効果を狙って大量に食べるのではなく、1日1粒程度を目安に取り入れるのが良いでしょう。
最近のトレンド:減塩+機能性梅干し
・スーパーや通販では、減塩タイプやはちみつ漬けなど食べやすく改良された梅干しが人気。
・「機能性表示食品」として、血糖コントロールや抗酸化をうたった梅商品も登場しています。
・海外でも「Umeboshi」がスーパーフードとして紹介され、和食ブームとともに注目されています。
栄養相談は日進市のたがやクリニックへ
梅干しは日本の伝統的な健康食品で、上手に取り入れれば疲労回復や生活習慣病予防にも役立ちます。ただし塩分量には注意が必要です。市販品を選ぶときはラベルをよく確認し、自分で漬けてみるのもおすすめです。健康志向が高まる今こそ、梅干しを“賢く”楽しみましょう。