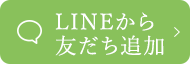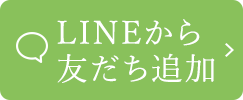親が糖尿病だと自分もなりやすい?|遺伝と生活習慣の関係とは
親が糖尿病だと自分もなりやすい?|遺伝と生活習慣の関係とは
健康診断などで「ご家族に糖尿病の方はいらっしゃいますか?」と聞かれた経験はありませんか?
これは、糖尿病の発症において「遺伝的要素」や「家庭環境」が大きな影響を与えることが知られているためです。
今回は、「親が糖尿病だと自分もなりやすいのか?」という疑問にお答えしながら、糖尿病のリスクと予防について解説します。
親が糖尿病だと子どもの糖尿病リスクはどのくらい?
いくつかの疫学調査によると、親が糖尿病を発症している場合、子どもも糖尿病を発症するリスクは高まることが分かっています。
たとえば、以下のような報告があります。
-
両親ともに糖尿病を患っている場合、子どもの糖尿病リスクは40%〜70%
-
片親のみが糖尿病の場合でも20%〜30%
また、日本人を対象とした研究(久山町研究など)でも、糖尿病の家族歴は独立した危険因子として報告されています。
糖尿病の「遺伝」はどのように関係している?
糖尿病は、生活習慣病の代表格とされる一方で、遺伝的素因が関与する多因子疾患とされています。
最近の研究では、日本人に特有の糖尿病発症リスクに関わる遺伝子の存在も明らかになってきました。
日本人に多い「インスリン分泌の弱さ」
糖尿病には、血糖を下げるホルモンであるインスリンの働きや分泌に障害が生じることで発症するタイプが多くみられます。
日本人は欧米人と比べてインスリンの分泌能力がもともと弱い傾向があり、少しの肥満や加齢で発症しやすい体質を持っているといわれています。
ゲノム研究からわかってきたこと
近年の大規模なゲノムワイド関連解析(GWAS)により、糖尿病に関わる多くの遺伝子変異が明らかになってきました。
東北メディカル・メガバンク(ToMMo)プロジェクト
-
東北大学が中心となって行っている東北メディカル・メガバンク計画では、15万人を超える地域住民のゲノム情報と生活習慣・病歴などを収集・解析。
-
その中で、日本人に特有の糖尿病関連遺伝子変異(KCNQ1やMAEAなど)が多数報告されました。
TOPIC(東北大学)による報告
TOPIC(Tohoku University Tohoku Medical Megabank Organization Project for Integrative Cohort)では、糖尿病発症に関する生活習慣と遺伝子の相互作用についての解析が進められています。
たとえば、肥満や運動不足などの環境因子と特定の遺伝子型が重なると、より高い発症リスクを持つことがわかってきました。
遺伝だけではない、生活習慣の影響
ただし、糖尿病のリスクは遺伝子だけで決まるわけではありません。
同じ家族で暮らしていると、食事内容や運動習慣などの生活習慣や環境要因も共有されることが多く、それがリスクに関与していることも忘れてはいけません。
例えば以下のような傾向があります。
-
高カロリー・高脂質な食生活
-
運動不足
-
不規則な生活や睡眠リズム
-
甘い飲み物やスナックの摂りすぎ
つまり、家族歴がある=必ず糖尿病になる、というわけではありません。
日々の生活習慣次第で、リスクを十分に下げることが可能です。
生活習慣の見直しでリスクは下げられる
実際に、アメリカ糖尿病予防プログラム(DPP)や日本の研究でも、体重の5~7%の減量や週150分以上の有酸素運動が糖尿病の発症リスクを大きく減らすことが示されています。
たとえば、
-
体重管理(BMIを適正に)
-
野菜中心のバランスのとれた食事
-
毎日のウォーキングや軽い運動
-
ストレスの少ない生活習慣の維持
など、小さな習慣を積み重ねることが将来の糖尿病予防につながります。
家族歴があっても、予防はできる ~日進市のたがやクリニック~
「親が糖尿病だったから、自分もきっとそうなるだろう」と諦める必要はありません。
遺伝的な要素は確かにありますが、それ以上に生活習慣の積み重ねが大きな影響を与えることが分かっています。
家族歴がある方こそ、今からの予防が大切です。気になる方は、お気軽にたがやクリニックまでご相談ください。