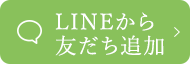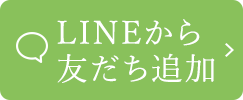足の裏にできたイボ、放っておいて大丈夫?原因と治療法を解説(日進市・長久手市・みよし市・東郷町)
足の裏にできたイボ、放っておいて大丈夫?原因と治療法を解説(日進市・長久手市・みよし市・東郷町)
足の裏にできた硬いできもの。押すと痛い、魚の目だと思って削ってみたけど治らない…。
その「できもの」は、ウイルス感染によってできる“足底疣贅(そくていゆうぜい)”かもしれません。
足裏のイボの原因・仕組み・治療法、そして再発を防ぐためのポイントについて解説します。
足裏のイボ(疣贅)とは?
足裏のイボは、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染によって生じます。
ウイルスが皮膚の微細な傷口から侵入し、角化細胞(ケラチノサイト)に感染して増殖します。
このとき、皮膚の免疫反応がウイルスを完全に排除できないと、細胞の増殖が続き「イボ」として現れます。
イボの表面は硬く、圧痛(押すと痛い)が特徴です。
魚の目・タコとの違い
魚の目(鶏眼)やタコ(胼胝)は、ウイルス感染ではなく物理的刺激による角質の肥厚です。
| 特徴 | イボ(疣贅) | 魚の目・タコ |
|---|---|---|
| 原因 | ウイルス感染(HPV) | 摩擦や圧迫 |
| 痛み | 垂直方向に圧迫すると痛い | 横方向に圧迫すると痛い |
| 表面 | ザラザラして黒点(血栓)がある | 滑らかで芯がある |
| 感染性 | あり(他人にも感染) | なし |
「削ったら黒い点が見えた」「増えてきた」という場合は、イボの可能性が高いです。
足裏にできやすい理由
足裏は、ウイルスが感染しやすい環境が整っています。
-
・常に圧力がかかり、角質が厚くなるためウイルスが潜みやすい
-
・汗や湿気で皮膚のバリアが低下しやすい
-
・プール・浴場・ジムの更衣室などで裸足になる機会がある
また、免疫力が低下している方(小児、ストレスが多い方、糖尿病や免疫抑制薬使用中の方)では、感染後にウイルスが長く残りやすいことが知られています。
イボの構造とウイルスの特徴
HPVは皮膚の表層(基底層)でのみ増殖し、血液中には出ません。
そのため全身感染は起こりませんが、局所での再感染を繰り返しやすい性質を持ちます。
顕微鏡的には、感染細胞の核内に「コイロサイト」と呼ばれる空胞変化が見られるのが特徴です。
この構造変化が、皮膚の盛り上がりやザラザラした質感を生み出します。
治療法:根気が必要です
① 液体窒素による凍結療法(標準治療)
マイナス196℃の液体窒素でウイルス感染細胞を破壊します。
治療後は軽い水ぶくれや痛みを伴うことがありますが、皮膚の再生とともにウイルスも除去されます。
再発を防ぐためには、複数回の通院治療(2〜3週間ごと)が必要です。
② 外用療法(角質溶解+免疫刺激)
サリチル酸ワセリンなどで角質をやわらかくし、感染層を少しずつ除去します。
自然治癒することもあるが…
一部のイボは、時間の経過とともに体の免疫がウイルスを排除して自然に消えることがあります。
ただし、治るまでに数か月〜数年かかることが多く、
放置すると他の部位に拡大・家族への感染・歩行時の痛みなどが生じるため、早期治療が推奨されます。
日進市のたがやクリニックへご相談ください
イボは見た目の問題だけでなく、「ウイルス感染症」という点が重要です。
削ったり市販薬で無理に除去すると、皮膚バリアが壊れ、感染が広がることもあります。
免疫力の維持(睡眠・栄養・ストレス管理)も大切で特に免疫低下が背景にある方では、繰り返しやすいため、丁寧な治療計画が必要です。
日進市・長久手市・みよし市・東郷町でイボの治療をご希望の方は、たがやクリニックまでお気軽にご相談ください。