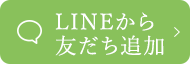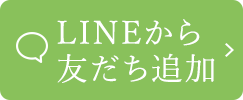転倒を防ぐ鍵は太ももの筋肉!大腿四頭筋を鍛える理由と日常でできる対策
転倒を防ぐ鍵は太ももの筋肉!大腿四頭筋を鍛える理由と日常でできる対策
加齢とともに「つまずきやすくなった」「階段がつらい」「立ち上がりが重い」と感じることはありませんか?
これらの症状の多くに関係しているのが、太ももの前側にある「大腿四頭筋」です。
転倒予防・自立した生活の維持に欠かせない大腿四頭筋について、医師の視点から解説します。
大腿四頭筋とはどんな筋肉?
4つの筋肉の総称
大腿四頭筋は、太ももの前面に位置し、以下の4つの筋肉で構成されています。
-
・大腿直筋
-
・外側広筋
-
・中間広筋
-
・内側広筋
これらはひざを伸ばす働きを持ち、立つ・歩く・階段を上るといった動作の要となる筋群です。
歩行・姿勢維持に欠かせない
大腿四頭筋は体重を支える「柱」のような存在であり、筋力が低下すると歩行スピードの低下、姿勢の不安定、転倒リスクの上昇を招きます。
大腿四頭筋が衰えると何が起こる?
転倒・骨折のリスクが上がる
特に高齢者では、大腿四頭筋の筋力低下が「転倒→骨折→寝たきり」につながる最大のリスク因子の一つです。
研究でも、大腿四頭筋の筋力は転倒発生率と強く相関することが報告されています(Age Ageing. 2014;43(1):84-90)。
階段の昇降や立ち上がりが難しくなる
椅子から立ち上がる・トイレ動作・段差を上るといった「日常動作」に必要なのがこの筋肉。
筋力低下が進むと、支えが必要になる→活動量が減る→さらに筋力が落ちるという悪循環に陥ります。
大腿四頭筋を鍛えることで得られる効果
転倒予防・歩行安定
筋力の維持・強化により、転倒リスクが減り、姿勢保持能力や歩行の安定性が向上します。
膝関節の痛み予防にも
大腿四頭筋は膝蓋骨(ひざのお皿)を安定させる役割も担っています。
筋力がしっかりしていると、膝への負担が減り、変形性膝関節症の進行予防にもつながります。
日常生活でできる大腿四頭筋の鍛え方
① 椅子スクワット
背もたれのある椅子に腰掛け、立ち上がる→座るをゆっくり繰り返します。
10回×2~3セットを目安に行うと効果的です。
ポイントは、膝がつま先より前に出ないようにすること。
② つま先立ち
台所や洗面所で支えを持ちながら、かかとを上げ下げするだけでもOK。
下肢全体の筋肉が活性化し、血流も改善します。
③ 階段を上る・歩く
特別な運動が難しい方でも、「階段を1段ずつ丁寧に上る」「少し速歩を心がける」など、日常生活の中で“使う”意識が大切です。
「筋肉の質」にも注目を
最近の研究では、筋肉の量だけでなく“質”の低下(脂肪の入り込み・神経伝達の低下など)も転倒リスクに関係すると報告されています。
大腿四頭筋の質を評価するには、体組成計の位相角(フェーズアングル)が有用とされており、たがやクリニックでも測定が可能です。
筋量と質の両面から、より科学的な転倒予防を行うことができます。
日進市のたがやクリニックへご相談ください
大腿四頭筋は、立つ・歩く・階段を上るなど、日常のあらゆる動作を支えています。
転倒を防ぎ、自立した生活を続けるためには、この筋肉をいかに維持するかが重要です。
たがやクリニックでは、筋肉量や筋質の測定、生活習慣のアドバイス、運動のサポートを行っています。
「最近足が弱った気がする」「転びやすくなった」と感じる方は、ぜひ一度ご相談ください。
筋肉の量だけでなく「質」も大事 体組成計でわかる健康の新指標