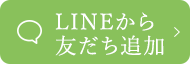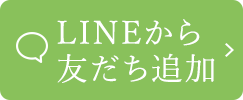骨粗しょう症とは? 2025年版ガイドラインをふまえてわかりやすく解説
骨粗しょう症とは? 2025年版ガイドラインをふまえてわかりやすく解説
骨粗しょう症とは
骨粗しょう症は、骨の強度が低下して骨折しやすくなる病気です。特に高齢者や女性に多く、背骨の圧迫骨折や大腿骨頸部骨折(股関節の骨折)などを引き起こすと、寝たきりや介護の原因になることがあります。
骨粗しょう症ガイドラインが10年ぶりに改訂(2025年版)
2025年、日本骨粗鬆症学会によって『骨粗鬆症診療ガイドライン』が10年ぶりに改訂されました。これは、2015年版と比べて多くの点でアップデートされており、次のような特徴があります:
-
骨折リスク評価の重要性が強調され、特に椎体骨折や大腿骨近位部骨折の既往がある方の治療が明確化。
-
新規薬剤の登場により、治療選択肢が拡大。
-
治療開始の基準や治療強度(第一選択薬・二次選択薬)がより具体的に。
-
骨密度だけでなく骨代謝マーカーや画像診断所見を活用した総合的な評価が推奨。
日本ではまだまだ骨粗しょう症診療が不十分
日本では、骨粗しょう症と診断されても、適切な治療を受けている方は全体の3割程度といわれています。また、骨折をきっかけに病院を受診することで初めて骨粗しょう症が判明する例も多く、未治療のままリスクが高まっているケースが少なくありません。
たがやクリニックでは、予防・早期発見・適切な治療を通じて、地域の皆さまの骨の健康を支えてまいります。
骨粗しょう症治療はここまで進歩しています
近年では骨吸収抑制薬(ビスホスホネート製剤やデノスマブ)に加え骨形成促進薬(ロモソズマブなど)といった新しい薬剤が登場し、治療の選択肢が増えました。
これにより、治療アルゴリズムも大きく変化し、骨折の再発防止や骨密度の改善効果が高い薬剤を優先的に使用する指針となっています。
特に「骨折ハイリスク」の患者さんには、治療の達成率が大幅に改善されていることが2025年ガイドラインで示されており、早期の介入が推奨されています。
骨粗しょう症が気になる方へ|たがやクリニックの取り組み
たがやクリニックでは以下のような診療を行っています:
-
骨密度検査による評価
-
骨折リスクの評価と治療方針のご提案
- 体組成計(inbody)でのサルコペニアの評価
-
必要に応じた薬物療法(注射・内服)
-
食事・生活習慣のアドバイス
-
他の病気(糖尿病・慢性腎臓病・関節リウマチなど)との併発管理
日進市をはじめ、長久手市・東郷町・みよし市の方からもご相談をいただいております。
寝たきり予防の第一歩は“骨の健康”から 日進市のたがやクリニックへ
骨粗しょう症は「治療できる病気」です。骨折予防=健康寿命の延伸にもつながります。
気になる症状がある方や、健康診断で骨密度が低いと指摘された方は、お早めにご相談ください。