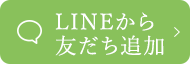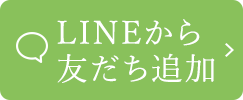CKD(慢性腎臓病)と飲酒 ~適度な飲酒はOK?専門医が解説~
CKD(慢性腎臓病)と飲酒 ~適度な飲酒はOK?専門医が解説~|たがやクリニック(日進市・長久手市・みよし市・東郷町)
CKD(慢性腎臓病)とは
CKD(慢性腎臓病)は、腎臓の機能が徐々に低下していく状態を指します。血液中の老廃物をろ過する能力が落ち、放置すると透析や腎移植が必要になることもあります。
生活習慣病(糖尿病・高血圧・肥満など)との関係が深く、生活習慣の見直しがとても重要です。
飲酒と腎臓の関係
アルコールは直接的な腎障害を引き起こすことは少ないものの、血圧上昇・脱水・代謝への影響などを通じて腎機能に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、糖尿病や高血圧などの合併症がある方では、飲酒によって血糖や血圧のコントロールが乱れやすくなる点にも注意が必要です。
CKD診療ガイドライン2023の見解
CKD患者に対する飲酒の推奨は明確ではない
日本腎臓学会の「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」では、
「CKD患者を対象とした観察研究が少なく、適度な飲酒量についての推奨は困難である」
とされています。
つまり、「一律に禁酒をすべき」とは言えない一方で、「積極的に飲酒を推奨できる根拠もない」というのが現時点での立場です。
適量の飲酒とCKD発症リスク
20g/日未満の飲酒はCKD発症を抑制する可能性
日本や海外の疫学研究をまとめたメタアナリシスでは、
少量~中等量(アルコール20g/日未満)の飲酒がCKD発症を抑制する可能性が示されています。
(Kelly JT, J Am Soc Nephrol 2021)
BMIによっても影響が異なる
標準体型(BMI 18.5~24.9)で適量飲酒(20g/日未満)の場合には、CKD発症のリスクがやや低い(HR 0.78)という報告があります。
一方で、痩せ型の方で過量飲酒(40g/日以上)をすると、むしろリスクが3倍以上に上昇(HR 3.21)するという結果もあります(Hashimoto Y, Sci Rep 2021)。
CKD患者における飲酒の注意点
① 血圧・動脈硬化への影響
過度の飲酒は血圧上昇を招きやすく、動脈硬化の進展につながります。
CKD患者ではもともと動脈硬化リスクが高いため、たとえ適量でも影響を受けやすい可能性があります。
② 脳・心血管イベントの増加
CKDの方では、一般人と比べて少量飲酒でも脳血管障害のリスクが上昇するという報告があります。
そのため、「腎臓が悪い=すぐ禁酒」ではなく、「合併症のリスクを踏まえて慎重に判断」することが重要です。
③ 薬との相互作用
降圧薬や糖尿病治療薬、脂質異常症薬などの効果に影響を与える場合があります。
専門医からのアドバイス
CKD患者に対して「絶対に飲んではいけない」とは言えませんが、
以下のような個別判断が大切です。
-
・飲酒する場合は1日20g未満(日本酒1合、ビール500mL、ワイン2杯程度)を目安に
-
・週に2日は休肝日を
-
・糖尿病・高血圧・脂質異常症を合併している方は主治医と相談を
-
・検査結果(クレアチニン、eGFR、尿蛋白)を定期的にチェックしながらバランスを取る
「以前は飲んでも大丈夫だった」という方でも、加齢や合併症によって許容量が変化します。
腎臓専門医としては、「飲み方を工夫して、腎臓を守る生活習慣を続ける」ことをおすすめします。
日進市のたがやクリニックへご相談ください
-
・適量(20g/日未満)の飲酒はCKD発症を抑制する可能性がある
-
・CKDをすでにお持ちの方では、安全な飲酒量のエビデンスは十分ではない
-
・合併症や体型により影響が異なるため、個別判断が重要
-
・過量飲酒は腎臓・心血管・脳血管に悪影響を与える