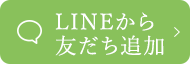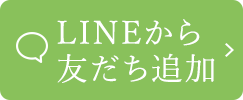蛋白尿はどこまで減らせばいいの?~日進市・長久手市・みよし市・東郷町の皆さまへ~
蛋白尿はどこまで減らせばいいの?~日進市・長久手市・みよし市・東郷町の皆さまへ~
蛋白尿とは?
蛋白尿は、腎臓の糸球体というフィルターに異常が生じ、本来は尿に漏れないはずの蛋白が出てしまう状態です。健診で「尿蛋白」を指摘されることも多く、慢性腎臓病(CKD)の進行や心血管疾患のリスクと強く関係しています。
蛋白尿の量と予後の関係
蛋白尿は「少なければ少ないほど腎臓にやさしい」ことが明らかになっています。
特に以下のカットオフ値が腎予後と関連します。
-
UPCR 0.5 g/gCr以上:腎機能悪化リスクが上昇
-
UPCR 1.0 g/gCr以上:末期腎不全や心血管イベントのリスクが顕著に上昇
一方で、蛋白尿を減少させることで腎機能の悪化や心血管イベントが減ることが多数の臨床試験で証明されています。例えば、RENAAL試験(ロサルタン)、IDNT試験(イルベサルタン)では、蛋白尿が減少した患者で腎不全への進行が遅くなることが示されました。
「どこまで減らすか」の目標値
臨床的な目安としては以下が参考になります。
-
0.3 g/日未満(UPCR < 0.3 g/gCr):腎予後は非常に良好
-
0.3〜0.5 g/gCr:比較的安定しているがさらなる低下が望ましい
-
0.5 g/gCr以上:進行リスクが高く、治療強化が必要
-
1.0 g/gCr以上:腎不全や透析導入リスクが顕著に上昇
つまり、蛋白尿は「できるだけゼロに近づける」ことが理想であり、UPCR 0.5 g/gCrを下回ることが治療の大きな目標となります。
SGLT2阻害薬の登場と新しいエビデンス
近年、糖尿病治療薬として開発された SGLT2阻害薬 が、腎臓保護薬として注目されています。
-
CREDENCE試験(カナグリフロジン):糖尿病性腎症患者を対象に、蛋白尿の減少とともに腎不全進行・透析導入・死亡のリスクを大きく減少させました。
-
DAPA-CKD試験(ダパグリフロジン):糖尿病の有無にかかわらずCKD患者で、蛋白尿の減少と腎予後改善が示されました。
-
EMPA-KIDNEY試験(エンパグリフロジン):軽度から中等度CKD患者において、腎機能低下と心血管イベントを有意に抑制しました。
これらの試験では、蛋白尿が減少するほど腎機能保護効果が高まることが明確に示され、治療目標の重要性を裏付けています。
原疾患ごとの違い
蛋白尿の意義や治療戦略は、CKDの原因によっても異なります。
-
糖尿病性腎症:微量アルブミン尿から心血管リスクが高まり、早期からの厳格な蛋白尿コントロールが必須。
-
IgA腎症:蛋白尿が1.0 g/gCrを超えると腎不全進行リスクが急増。免疫抑制やRAS阻害薬・SGLT2阻害薬を含めた集学的治療が検討されます。
-
高血圧性腎硬化症:蛋白尿が出現していれば予後悪化因子となるため、降圧・減塩とともに蛋白尿低下を目指します。
まとめ
蛋白尿は腎臓病の「バロメーター」であり、少なければ少ないほど腎臓と全身の健康を守ることにつながります。特に UPCR 0.5 g/gCrを下回ることを目標に、可能な限り蛋白尿を減らすこと が腎不全や心血管イベントを防ぐ鍵です。
健診で定性検査にて「尿蛋白+」を指摘された場合、まずは定量的に尿蛋白を評価することが大切です。さらに尿蛋白が 0.5 g/gCr以上であれば、原因を突き止め、その治療を行い、尿蛋白が減少しているかどうかを確認すること が必要です。
蛋白尿の評価と治療は、腎臓専門医の知見が活かされる領域です。日進市・長久手市・みよし市・東郷町にお住まいで蛋白尿を指摘された方は、ぜひ当院にご相談ください。